~晩夏 サヴァン ~ ②
そのままの
「海は荒海 むこうは佐渡よ」…
ずいぶんと息が長く続いているなと、歌いながら気づいた。
力まずに歌っている。
視界いっぱいの海、
そして砂州のすっと伸びる感じが、
そのまま、歌になっていた。
ちょっと急いだり すうっと伸ばしたり、
その自由自在な感じが楽しくなってきた。
長いフレーズ
大学での声楽の授業を思い出した。
味わいを保ちつつ、
小さいボリュームで息を長く歌い続けることに、
難儀した記憶がある。
でも今は、
ひと息で、弱音での長いフレーズを歌いきれている。
これを あの声楽レッスン場で、
またはコンサートホールで実行したなら、
この目の前に広がる海を思わせる歌声を 披露できるような気がしてきた。
コンサートホール?
いやいや、緊張してしまって、
伸び伸び歌うどころじゃ なくなるだろうけれども。
緊張
演奏家は、たった一度の発表のために、長い時間をかけて練習を重ねる。
そして、積み上げた研鑽の成果を、聴衆に届ける。
緊張に負けないということも、
日々の鍛錬の先にあると思う。
私がステージ上でソロを担当したことはあるが、
緊張のあまり、練習通りには実行できなかった。
会場に響く声が、自分ひとりきりだと自覚した段階で、
その状況に吞まれずに力を発揮するには、
それ相応の熟練が必要だと思う。
本番は練習の8割ができたら十分だという説もあるし。
固有の存在感
健一の歌声を思い出した。
固有の存在感を伴いながら長く伸びる歌声だ。
緩急、抑揚のつけ方が卓抜していて、
歌詞の意味するところや旋律の魅力を味わわせてくれる。
それは、他のどの声楽家とも違っていた。
特に、西洋音楽と密接に関わる宗教曲については、
それこそ天に届くかのように、
立ち昇るような表現を聴かせてくれたものだ。
自由に、惜しみなく
健一は、どんなに大規模なステージであっても、
緊張した様子など見せたことがない。
大観衆を前にして委縮するなど、
全くなかったと思う。
かといって、自分に酔いしれているという感じでもない。
不要な緊張などなく、
旋律の求めに応じて、ある意味淡々と、
音楽表現上 期待されることを、
自由に、惜しみなく実行している印象だ。
健一にとっての聴衆
健一は、「『そもそも、聴くつもりで この場にいる人』に聴かせることに なんの配慮(遠慮?緊張?)が必要か」、
と言っていた。
聴衆とは、言うまでもなく、
人間の集まりだ。
でも健一にとっては「人間」に見えているのだろうか?と思えたものだ。
人はたいてい、自分の周囲の人間に対して、
信頼したり不安を感じたりと、
なんらかの感情を抱くし、
聴衆に対して抱く何某かも あるように思うが、
健一にとっては、どうなんだろう。
いしむら蒼




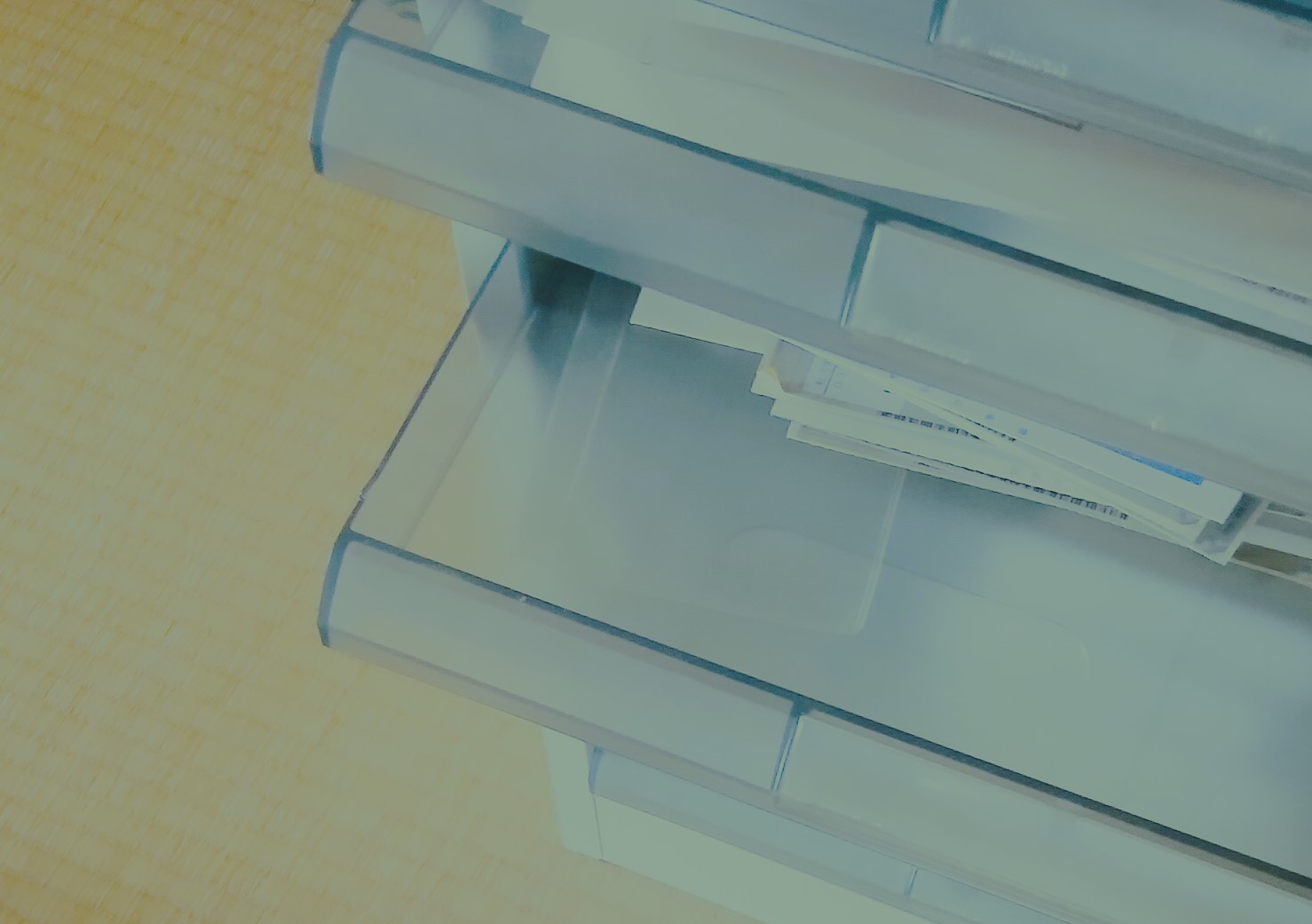

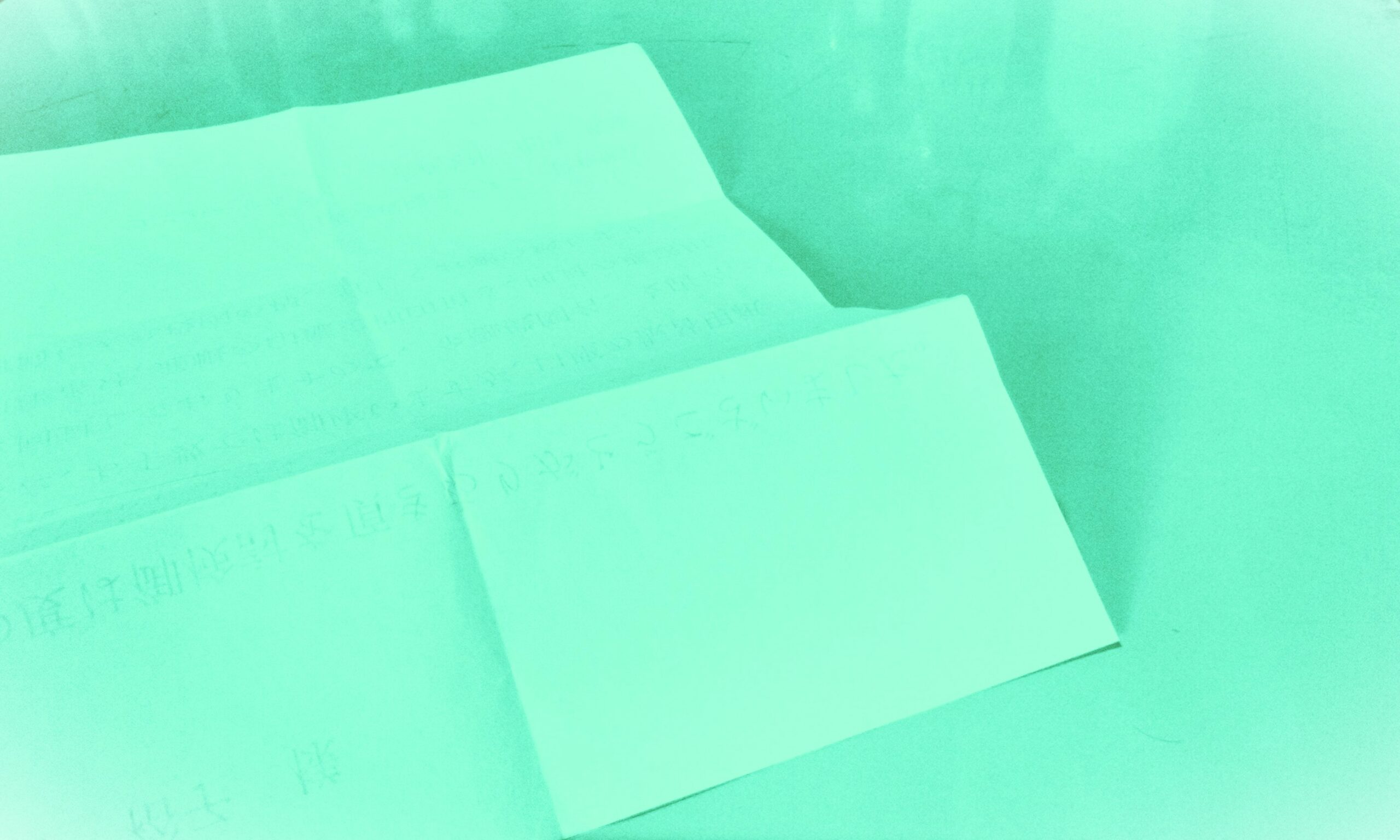

“サイコパスの妻 2-② 息の長い弱音” への1件のフィードバック