~晩夏 サヴァン ~ ③
健一にとっての他者
健一自体について、
ある意味「人間」とは思えないような違和感を覚えたのは、先月半ばのこと。
そういえば、健一にとっては、
「他の人」はどういう存在なんだろう。
他者への「共感」というものが感じられない、
と、思ったこともあった。
私の気持ちにも子供らの気持ちにも、
寄り添ってもらえた実感が薄く、
私達家族は、健一にとって「添え物」にすぎない?とも、思えたのだった。
人の集合体
また、健一はその時々 目についた興味深いものに、
すぐ夢中になる。
近くの誰かが戸惑っていても 意に介さないという場面は、
これまで何度もあった。
それは、私達家族のみならずのこと。
人に対する感情、情緒、それらが鈍い?
いや、極端な言い方だけど、
ない?ようにすら思える。
それは人の集合である聴衆に対しても、
そうなのではないか。
とすると、
大観衆を前にしても緊張しないのも、当然かもしれない。
まっすぐ
健一は、自分が追い求めるものに対し、
「まっすぐ」だ。
手前に何があってもスルーしている。
わざと排除しているんじゃない、
聴こえていない、
見えていないように思える。
ステージ上の健一には、
目の前の観客が目に入っていないかのようにも、思えた。
(観客を意識して)緊張することがないのも含め、
どんな障害や雑音があっても、
気を取られることがない。
何もないまま
いま、私は、「息の長い歌」を実行できた。
たまたま。
自分史上 初めてと言っていいほどの長さのそれを。
車内なので緊張がないのは もちろんのことだけれども、
その長いひと息の中で、
歌詞や曲調を生かして 自由に抑揚をつけて歌えた。
目の前に拡がる海と、
やりとりをするかのように歌えた。
私と「歌」の間は、
すっと直結していたように思う。
私と海の間には、
私と歌の間には
何もないままだった。
そんな感じを受ける。
考えるべきこと
本来、一曲を演奏するにあたり、
考えるべき要素はたくさん ある。
例えば「この高音を出すには、事前準備が必要」とか、
「母音の違いによって 響きが不ぞろいにならぬよう」だとか、
「以前の失敗を改善しよう」
「聴衆から評価されやすくしよう」
「繰り返すリズムや音型は 計画的に違いを演出しよう」
「揺れずに持続するためには、腹筋をどう保とう」
「ビブラートの頻度や細かさをどうしよう」
…などなど。
今、私が歌った「砂山」は、
それらをどれも 考えないまま歌ったものだった。
迷いもなかった。
間に何も はさまずに歌を紡ぐ…
これは、「健一の歌」に近いかもしれない?
などと思えた。
いしむら蒼


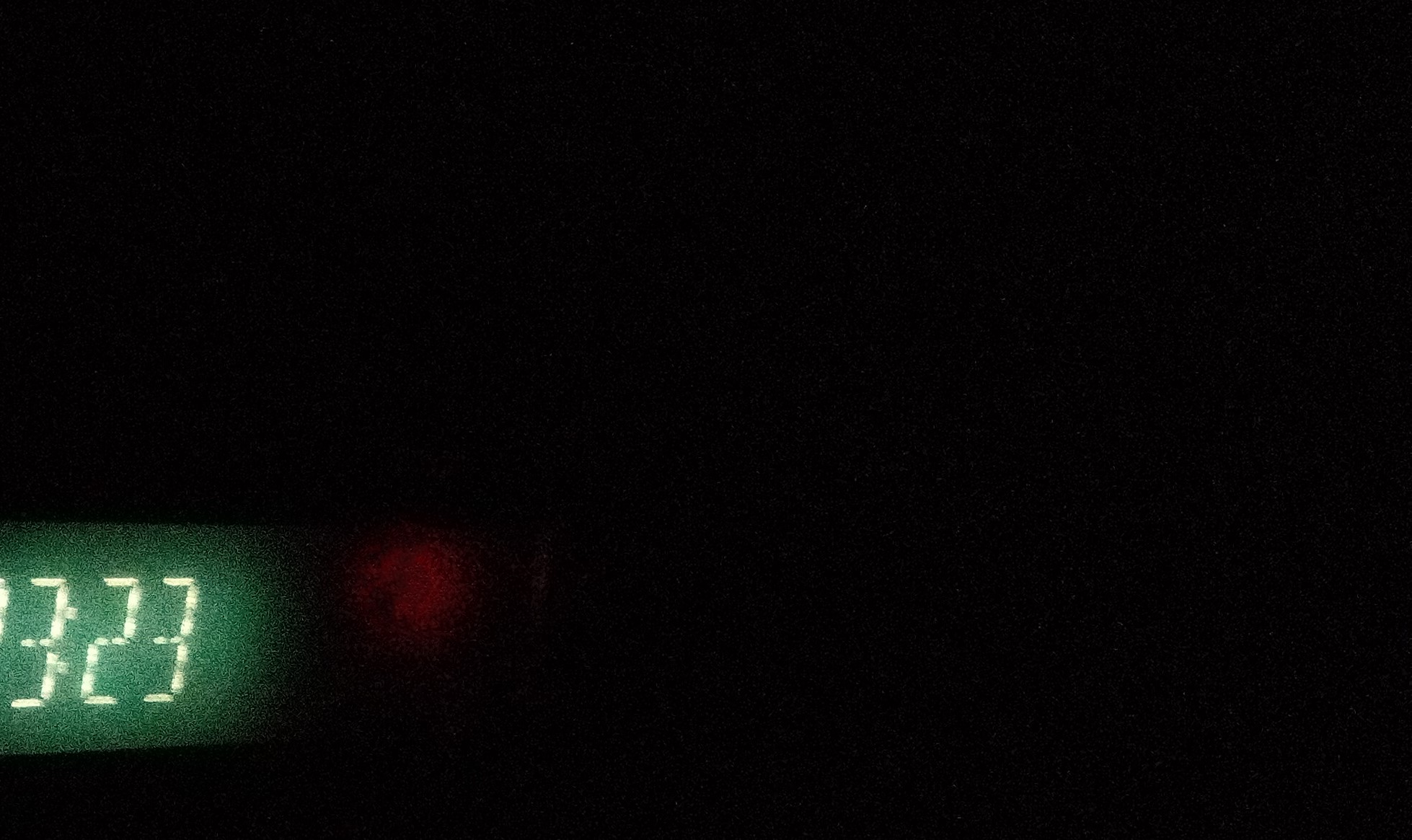





“サイコパスの妻 2-③ 手前にあるもの” への1件のフィードバック